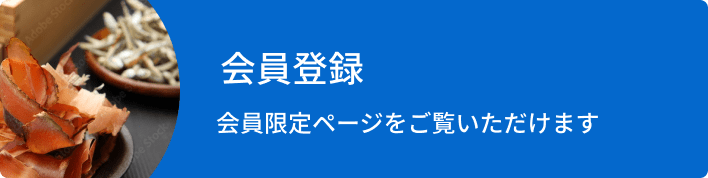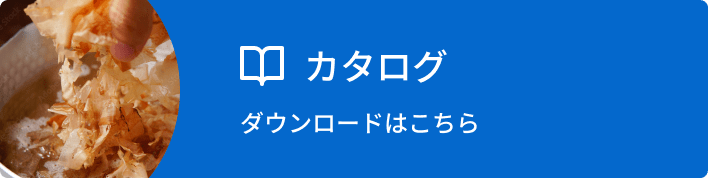おいしさづくりの基礎知識
おいしさづくりの基礎知識
てり・つや~その発現と向上方法~
見た目のおいしさを決める要素
店頭で食材や惣菜を選ぶ際、「見た目のおいしさ」は購入の判断材料としてとても重要です。 「おいしそう」、「食べてみたい」と感じられる見た目の要素には、下記が挙げられます。 ・てり・つや ・色味(彩り、焼き色、容器、鮮度、調理感など) ・煮崩れの有無 ・盛り付け方 ・具材の切り方、サイズ これらの中から、このページでは「てり・つや」についてご説明します。 他に、「焼き色」、「煮崩れ」についてのページもありますので、是非ご覧ください。
てり・つやから連想されるおいしさ
ここにA、B、2つのぶりてり焼きの写真があります。 どちらがよりおいしそうに見えるでしょうか?
Bの方がてり・つやがあり、おいしそうに見えたのではないでしょうか。 てり・つやは、出来立て感やしっとり感といったプラスのイメージを連想させ、見た目のおいしさに繋がります。逆に、てり・つやがないと、表面が乾いたような見た目となり、作ってから時間が経っていそう、パサついていそうなど、あまりよくないイメージに繋がってしまいます。 このように、食品の見た目において「てり・つや」は重要な要素です。
てり・つやの発現
では、食品のてり・つやはどのようにして生じるのでしょうか。 料理にてり・つやをつけるために用いられているものとしては、糖類、卵黄、油脂などが挙げられます。その中でも、和食では砂糖や本みりんなどの調味料が多く使われ、てり焼きや煮物の調味液には糖類を配合します。 糖類によるてり・つやの発現には、主に下記2つのメカニズムが考えられています。 ・糖類が水分を保持することで具材の表面がぬれた状態になり、てり・つやが生じる。 ・糖類がアメ(ガラス状態)になり、表面が滑らかになることで、てり・つやが生じる。 糖類でてり・つやをつけるためには、使用する調味料に様々な種類の糖類が含まれている方が効果的といわれています。 様々な糖類を含む本みりんは、より効果的にてり・つやをつけることができる調味料です。
出典
- 河辺 達也、森田 日出男,『みりん(2)』,日本醸造協会誌,93巻11号,863-869(1998)
- 大谷 貴美子 他,『つやに関する基礎研究 糖溶液塗布面の加熱によるつや』,日本調理科学会誌,33巻4号,441-450(2000)
- 大谷 貴美子,『視覚情報による「おいしさ」の研究』,日本調理科学会誌,43巻2号,57-63(2010)