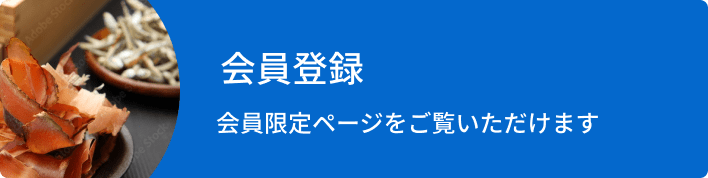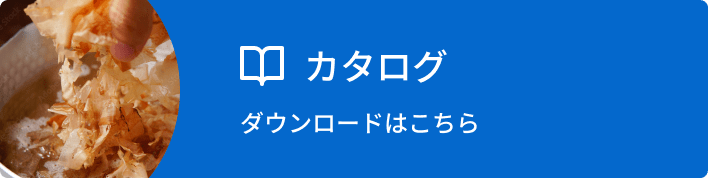おいしさづくりの基礎知識
おいしさづくりの基礎知識
減塩商品の開発と工夫~おいしさを向上させる方法~
減塩商品の開発
近年、健康志向の高まりから低塩・減塩ニーズが増加し、減塩商品の開発が活発に進められています。しかしながら、塩分を減らした減塩食は、物足りなく、おいしくないというイメージをもたれてしまいがちです。そこで、減塩商品の開発の際は、おいしさを維持するために下表のような方法がとられています。
塩化カリウムの使用
食塩(塩化ナトリウム)の摂取を控えるため、代替塩としてよく用いられるものが塩化カリウムです。塩化カリウムは食塩と同じ感覚で使える利便性がある反面、塩味と同時に苦味やえぐみも伴うため、使い方によっては食品そのもののおいしさを損なってしまう可能性があります。 このような問題を解決するため、塩化カリウムの苦味やえぐみを抑制するマスキング素材の開発が進んでいます。塩化カリウム製剤の中には、マスキング素材と混合して使いやすくしたものもあります。
味つけの工夫
味つけの工夫で減塩効果を期待することもできます。方法を4つご紹介します。 ●うまみやコクの増強 うまみやコクを増強して味の広がりを強めることで、減塩による味の物足りなさが緩和されます。使い勝手の良い出汁の活用がおすすめです。 ●酸味の活用 酸味をつけることによって味にメリハリが生じ、塩味の薄さを補うことができます。 ●香辛料の活用 香辛料は、華やかな香りを付与するだけでなく、料理の味を引き締めたり、素材の風味を引き立てたりします。減塩による薄味の物足りなさを補います。 ●とろみの活用 調味液にとろみをつけると食材への味絡みが良くなり、また、調味液が舌にまとわりやすくなるため、味を濃く感じさせることができます。
調味料由来の塩分を減らす
調味料の種類によっては、知らないうちに塩分を余計に使用していることがあります。 ●例:料理酒 一般に「料理酒」と呼ばれているものは、その種類や製造方法によって「酒類調味料」と「食品調味料」に分けられます。 酒類調味料の料理酒に食塩は含まれませんが、食品調味料の方は食塩を含み、塩分が2%程度のものもあります(海水の塩分濃度は約3%) 。 商品ラベルに「料理酒」と書かれたものの多くは、食塩を含む食品調味料です。 一方、ラベルに「清酒」と書かれているものは酒類調味料で、食塩を含まないため余計な塩分摂取を抑えることができます。 減塩のためには、「清酒」と書かれた料理酒を選んで使用することをおすすめします。
●例:みりん 「みりん」として使われる調味料にも、料理酒と同様に食塩を含むものと含まないものがあります。食塩を含むものは、「醗酵調味料」と呼ばれる食品調味料で、製造工程で食塩を加えています。 商品ラベルに「みりんタイプ」と記載あるものが該当し、塩分が約2%含まれます 。これら調味料を使うと、想定より多くの食塩を使用することになります。 減塩を意識する際は、食塩の入っていない本みりんがおすすめです。
出典
- 伏木 亨 編著,『光琳選書① 食品と味』,光琳
- 『減塩するならこの一冊 塩分一日6gの健康献立』,女子栄養大学出版部